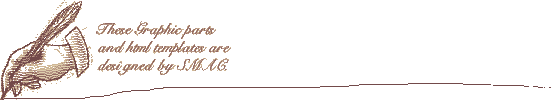辞書と経典だけは別格で、七冊までは持ち込んでもよい。
それを聞いた時には快哉を叫びそうだった。
状況を忘れたのは一瞬で、俺はすぐさま理性を取り戻す。弁護士に使い慣れた辞書の差し入れを頼み込んだ。今まで使っていた物に関しては、持ち込みまでに検査が入るため、手元に来るのはかなり遅くなるという。ならばと八重洲のブックセンターに入っている物を買ってくれるよう頼む。アマゾンでもいい。すらりと口から使い慣れた辞書の詳細が飛び出して驚いた。今まで意識して使っていたことなどなかったのに。
それで自分がどんなにもミステリを書くことにとらわれているかを思い知った。あらためて。
手元に置いておけるノートの数にも制限がある、この場所で。
そして、その中身すら、建前はともかく現実には自分だけのものとはならず、絶えず人目にさらされる、状況で。
ミステリを書こうとしている。人が殺される話を。
それは俺の置かれる状況を、さらに悪くするだろうと知っている。
非難もあるだろう。自分自身の内側を見つめれば、後ろめたさも罪悪感も、良識に反しているとの思いもある。
愚かでしかない。
それでも書かずにいられない。
どうしようもなく愚かだ。
そんな自分をきちんとわかっていれば、殺さずにいられただろうか。
敬愛する大先輩、情人でもあった、最期まで真の意味でライバルにはなりえなかった作家を。
脳裏では、彼の最期の作品が、毒のように誘惑をささやく。私を書け、書け、と。
書いてはやらない。
俺は俺の話を書く。
こんな風に、また書くことができるとは思いもしなかった。
誰も読まないだろう話、けれどひとりだけは読んでくれることを知っている。
なあアリス、俺も書かずにいられない。馬鹿だよな、もっと早くに気づけばよかった。
視線の先には、今読んだばかりの分厚い本がある。
拘置所に持ち込める本は、たった三冊。他のものが読みたければ入れ替わりに、今持つ本を差し出さなくてはならない。けれど、しばらく、この一冊はこの部屋の中にあり続ける。
献本された新刊だ。差し入れられて、むさぼるように中身を読んだ。
ひとごろしという罪を犯した同期に渡すには、誰もがためらうはずの本を衒いもなく送ってよこした作家の意図は明らかだ。穏やかで優しげな顔をして、彼の中にある業は深い。
彼もまた、どんなことがあったとしても書き続けていくのだろう。
ノートを開く。
学生時代に戻ったみたいだと心の奥でわらう。
パソコンも、ワープロもなかったころと同じように。
脳裏に渦巻く物語をこの指先で紡いでいくのだ。
ペンを持つ。
ふるえる手で、最初の一字を刻んだ。
了 (2009.12.26 彩)